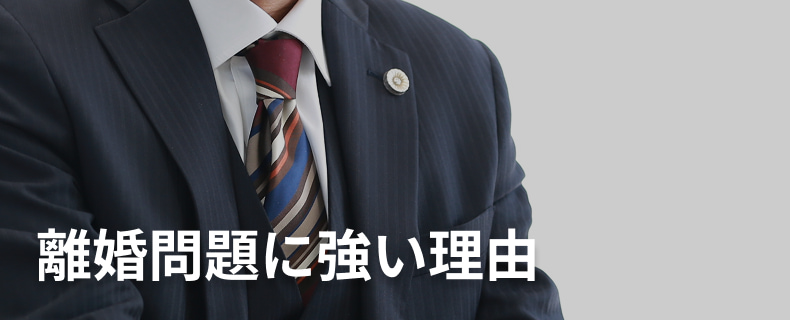昨今は、DNA鑑定が身近になり、比較的安価で簡便に親子関係調査をすることができるようになってきました。これに伴い、「托卵(たくらん)」という言葉を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
托卵とは、生物学において、カッコウなどの鳥が、他種の鳥の巣に卵を産み付けてその子を育てさせる行為を指します。残酷なことに、同様の行為が人間関係においても起きるようになっているのです。
仮にあなたの奥様が他の男性と不貞・不倫をして、その結果生まれたお子さんを“托卵”されていたとしたら……。
このような場合の精神的なショックは計り知れません。また、あなた自身、離婚や慰謝料、子どもの親権・監護権や養育費など、様々な法的問題に直面することになります。
この記事では、托卵と離婚について、弁護士の視点から解説していきます。
目次
1. 托卵は離婚事由になるか?
まず結論から述べますと、托卵は、離婚事由になりえます。
端的に、托卵がなされているということは、妻側に不貞行為があったことを示します。このため、民法770条1項1号に記載された「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当することとなり、法律上、離婚事由があると認められることとなります。
加えて、民法770条1項5号記載の、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」も認められる可能性があります。
このように、托卵は、托卵の事実自体を証明すれば不貞行為があったことを示すことができるので、離婚事由になります。
2. 托卵が疑われるサイン
それでは、このような托卵が疑われるサインについてもご説明します。
托卵は、多くの場合、夫が子どもの成長過程で抱く違和感から発覚します。以下のようなサインがある場合、托卵を疑うきっかけとなるかもしれませんので、ご注意ください。
2-1. 子どもの顔や血液型
まずはやはり、子どもの顔が自分や妻、どちらの親族にも似ていない場合には、違和感が生じやすいでしょう。ご自身も妻も一重なのに、二重の子どもが生まれてきたなど、遺伝的特徴からもサインは読み取れます。
同様に、子どもの血液型が、両親の血液型から遺伝的にありえない組み合わせである場合にも、注意が必要です。例えば、ご両親のどちらかがAB型の場合には、基本的にはO型のお子様は生まれません。両親の血液型から想定されない血液型の子どもである場合、托卵の可能性が非常に高まります。
2-2. 妻の妊娠時期と性行為の時期が合わない
また、妻の妊娠時期に、夫婦間の性行為がほとんど又は全くなかったという場合や、妊娠時期と性行為の時期にずれがある場合には、托卵が疑われます。妻側は妊娠時期をある程度ごまかしてくるでしょうが、出産予定日を聞いた時点で「あれ?」とお気付きになる事例もあります。
例えばあなたの出張中・単身赴任中に妊娠したと思われる場合には、托卵の可能性が極めて高いといえるでしょう。ここまであからさまな托卵行為をする女性は稀ですが、それでも注意が必要です。
2-3. 妊娠前に不倫の兆候があった
妻に妊娠以前から不倫を疑わせる行動があり、例えば、帰りが遅い、LINEやメールを隠れてしている、急におしゃれになったなどの兆候があった場合にも、妊娠との関連性を考える必要があります。特に、不貞相手と思われる男性からの連絡を目にした場合には、留意しましょう。
托卵は不貞行為が存在して初めて成立する行為ですから、不貞行為自体が疑われる場合には細心の注意が必要といえます。
もちろん、これらのサインはあくまでも疑いを持つきっかけであり、それだけで托卵と断定することはできません。しかしながら、例えば複数のサインが重なる場合や、明らかに妊娠時期が不自然である場合などには、慎重な対応が求められます。
3. 托卵が疑われる場合の対応
それでは、托卵の疑いが生じた場合には、どうしたらよいのでしょうか。
まずは托卵の疑いがある場合、感情的になることなく、冷静に事実確認を進めることが重要です。もちろん、暴力を振るったり暴言を吐いたりすることは、あなたにとってマイナスに作用しますから、控えてください。
3-1. 証拠を集める
まずは、離婚や慰謝料請求を有利に進めるために、客観的な証拠が不可欠です。托卵や、不貞行為の証拠を集めましょう。
最も重要な証拠は、あなたとお子様との間に生物学上の親子関係がないことを示す資料、つまりDNA鑑定資料です。あなたとお子様との間に親子関係がないことさえ分かれば、托卵の存在と不貞行為の双方を示すことができます。DNA鑑定をすること自体に心理的な抵抗が生じるでしょうが、奥様との間での離婚等を検討するのであれば、必ず証拠を収集しましょう。
また、特に、托卵をする女性は、不貞相手との間の子どもを産むほどに、不貞相手に対する愛情が深いといえます。このため、多くの事例で、女性側が、托卵しているお子様を不貞相手に会わせるといった行動を取ります。こういった状況を証拠に収めることも重要です。
これらの他にも、不貞行為自体の存在を示す証拠資料も集めることができると、なお有利になります。
3-2. DNA鑑定
上記のとおり、托卵を確定的に判断する最も有効な手段はDNA鑑定です。子どもと夫、そして可能であれば妻のDNAを比較することで、生物学的な親子関係の有無を明確にすることができます。
DNA鑑定を行う際は、必ず信頼できる専門機関に依頼し、正確な結果を得るようにしてください。昨今は、比較的安価にDNA鑑定をすることができるようになってきていますが、裁判所に提出して信用してもらえる程度の精度は必ず必要となります。
もしご不安であれば、DNA鑑定業者を知っている弁護士にご相談をいただき、弁護士から業者の紹介を受けても良いかもしれません。
3-3. 弁護士に相談する
証拠を収集しながら、又は証拠を収集したのちは、早い段階で弁護士に相談しましょう。
托卵は、法的に複雑な問題を含みます。証拠収集の方法、DNA鑑定の進め方、そしてその後の離婚手続や慰謝料請求など、問題を解決する上で、法律上の専門的な知識が不可欠です。とりわけ托卵行為に気付いた場合の精神的負担の大きさを踏まえると、ご自身のみで対応されることはあまりにも苦しい事態を招きかねないと言わざるを得ません。
ぜひ、托卵の疑いが生じた段階で、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況に応じて適切なアドバイスを提供し、今後の手続を円滑に進めるためのサポートをします。つらい現実に苦しむあなたと共に、相手方との協議を重ねる伴走者ともいえます。
3-4. 嫡出否認の訴え
DNA鑑定の結果、子どもがあなたの子ではないと判明した場合、夫側は嫡出否認の訴えを提起することができます。
そもそも法律上、婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。これを「嫡出推定」と呼びます(民法772条)。この嫡出推定を覆すためには、子又は親権者である母を相手に、嫡出否認の訴え(民法775条)を提起し、裁判所の判決を得る必要があります。
但し、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から3年以内に提起しなければなりません(なお、令和6年4月1日より前に生まれた子どもについては、子の出生を知った時から1年以内の訴訟提起が必要です。)。また、子の出生後に嫡出子であることを承認した際には、嫡出否認の訴えを起こすことができなくなります。これらの制限があるため、妊娠中から托卵のおそれを感じていた場合には、早い段階で弁護士にご相談をいただくべきといえます。
4. 托卵と親権
托卵が判明し、夫が嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えなどを提起して勝訴した場合、法律上、子どもは夫の子ではないことになります。この場合、夫は子どもの親権者になることはできません。親権は生物学上の親である妻が持つことになります。
しかし、そうでない限りは、生物学上の親子関係が否定されても、法律上の親子関係は存続します。このため、托卵を受けた子どもであっても、敢えて法律上の親子関係を否定するような手続を取ることを避ければ、夫側にも親権が認められます。もちろん、離婚後の親権(改正後の民法による共同親権も含む。)を獲得できることもあり得ます。
托卵されたお子様との関係がどうであるのかによって、取るべき法律上の手続が大きく変わってきますので、ご注意ください。
5. 托卵と慰謝料
ちなみに、托卵が判明し、これを証明できた場合、夫は妻に対して慰謝料を請求することができます。この慰謝料は、妻の不貞行為それ自体と、夫を欺いて他人の子を育てさせたことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。このため、不貞行為が行われた期間・不貞相手との関係性や、托卵をしてきた期間などによって、慰謝料額は大きく変わります。
また、不貞相手が托卵の事実を知っていた場合、夫側としては、不貞相手に対しても同様に慰謝料を請求できる可能性があります。上記のとおり、托卵をしたのちも妻と不貞相手との関係は、子どもを巻き込みながら続くことが多いですから、不貞相手にもその責任を取らせるべきといえるでしょう。
慰謝料請求の具体的な金額や手続については、弁護士に相談していただき、適切なアドバイスを受けるようにしてください。
6. 托卵と養育費
また、養育費についてもご説明をします。
上記のとおり、仮に托卵が発覚したとしても、嫡出否認の訴えや、親子関係不存在確認の訴えなどの法的手続を取らない限り、法律上の親子関係は消えません。このため、仮に離婚したとしても、夫には托卵された子どもへの養育費支払義務が残ることとなります。この場合、通常の離婚と同様に、夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢などに基づいて養育費の金額が決定されます。
この場合には、生物学上の親である父(不貞相手)に対して養育費を請求することは困難ですので、ご注意ください。
他方で、托卵が判明し、夫が嫡出否認の訴え等を提起して勝訴した場合、法律上、子どもは夫の子ではなかったと扱われるため、夫側に養育費を支払う義務は生じません。
7. まとめ
以上のとおり、托卵と離婚についてご説明をしました。托卵は、単純な不貞行為以上に、夫婦関係を根本から揺るがす深刻な問題です。もし托卵の疑いがある場合は、感情的にならず、冷静に、そして迅速に対応することが重要です。
DNA鑑定等の結果、托卵が事実であった場合、あなたは、離婚、慰謝料、親権、養育費など、様々な法的問題に一気に直面します。もちろん、精神的動揺も激しいものとなるでしょう。この場合には、信頼できる弁護士と協力しながら、ご自身の権利を守り、今後の人生を再構築するための最善の道を見つけることが大切です。
当事務所では、最新の法制度にも留意しながら、多くの離婚事件を手がけております。托卵の疑いを持たれた場合や、托卵の事実が判明した場合には、ぜひ、早い段階で当事務所にご相談ください。当事務所では、家事事件・離婚事件に慣れた弁護士が、あなたに寄り添いながら丁寧に対応します。あなたからのご相談をお待ちしております。
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。