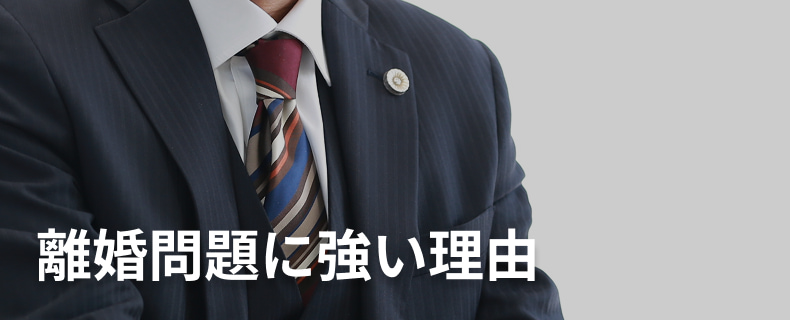夫婦関係が修復不可能となり、離婚を決意した際、多くのケースで次のステップとなるのが「別居」です。別居は、単なる生活環境の分離にとどまらず、法的な離婚手続、特に離婚調停を有利に進めるための戦略的な意味合いも持っています。
このページでは、弁護士の視点から、別居後に離婚調停を申し立てるメリット、その際に踏まえておくべき重要な注意点、そして調停手続の具体的な流れについて解説します。
目次
1. 別居後に離婚調停をするメリット
別居という行動は、離婚を求める側にとって、精神的、法的、経済的な面で複数のメリットをもたらします。
1-1. 長期間の別居は「離婚原因」となりやすい
まず、日本の民法では、相手が離婚に同意しない場合、裁判で離婚を成立させるためには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といった法定離婚事由が必要です。
長期間の別居は、夫婦としての共同生活がすでに破綻しており、修復の見込みがないことを示す、最も客観的で強力な証拠となります。別居期間が複数年に及んでくると、裁判所は夫婦関係が破綻していると判断しやすくなります。
また、離婚調停は話し合いの手続ですが、調停委員は将来の裁判の見通しを踏まえて双方に働きかけます。別居が長期間に及んでいる事案であれば、「裁判になれば離婚が認められる可能性が高い」という圧力を相手方にかけるとともに、調停委員にも離婚が妥当と考えさせることができますから、早期の離婚合意を促す大きな要因となります。
1-2. 冷静に話し合える環境ができる(特にモラハラやDVの被害がある場合)
また、同居状態での離婚協議は、感情的な対立や衝突が生じやすく、建設的な話し合いが困難になりがちです。この点でも、別居は有利にはたらきます。
特にモラハラ(精神的暴力)やDV(身体的暴力)の被害を受けている場合、別居は被害者側の心身の安全を確保し、同居のストレスから解放されるために必須の手段です。
離婚調停では、調停委員が間に入って意見調整を行うため、当事者が直接顔を合わせる機会は最小限に抑えられます。別居により精神的に落ち着いた状態が確保できれば、弁護士と連携しながら調停で冷静に離婚条件の交渉に臨める環境が整います。弁護士が代理人として交渉を担うことで、感情的な消耗を避け、法的に有利な主張を貫きやすくなるのです。
1-3. 婚姻費用を請求することができる
夫婦には、別居中であっても、互いに生活を助け合う義務(相互扶助義務)があります。この義務に基づき、収入の多い方(主に夫側)に対して、別居後、自分や子どもの生活費である「婚姻費用(こんいんひよう)」の分担を請求することができます。
別居後、相手方が生活費を支払わない場合、離婚調停と同時に、または別に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。婚姻費用は、請求した時点(調停申立て時など)から支払いが命じられるため、別居後は速やかに調停を申し立てるべきです。
この手続で婚姻費用が確保されることで、経済的な不安が軽減され、安定した生活基盤の上で離婚手続に専念できるというメリットを得ることができます。また、相手方にとっては、婚姻費用の支払が継続的な経済的負担となり、早期の離婚に応じる動機付けにもなり得ます。
2. 別居後に離婚調停をする時の注意点
以上のメリットがありますが、別居が法的に不利に作用しないよう、手続を進める前に以下の重要事項を徹底する必要があります。
2-1. 別居理由の証拠を用意する(悪意の遺棄とみなされないために)
まず、夫婦には同居義務があるため、正当な理由のない一方的な別居は「悪意の遺棄」(相手方を意図的に放棄する行為)とみなされ、法定離婚事由の一つに該当するとして相手方から慰謝料請求を受けるリスクがあります。
こういった事態を防ぐために、別居が「悪意の遺棄」ではないと証明するためには、DVやモラハラ、不貞行為(浮気・不倫)など、別居せざるを得ない正当な理由の証拠を事前に確保しておくことが極めて重要です。
証拠の例としては、医師の診断書、被害状況を記録した日記、録音、不貞行為を示す写真やメールなどが挙げられます。
また、別居に際しては、一方的に家出するのではなく、別居の理由と意思をメールやLINEなど記録が残る形で相手方に伝えておくことが望ましいです。こうすることで、一方的な遺棄行為であると見られないようにしましょう。
2-2. 財産の把握をしておく
また、離婚時に財産分与を正確かつ公正に行うため、別居前に夫婦の共有財産(預貯金、保険、不動産など)の全体像を把握し、その証拠資料を確保しておく必要があります。
別居後は、相手方名義の財産資料を任意で提出させるのは困難になることが多いため、同居中に以下の資料のコピーや写真で控えを取っておくべきです。
- ・預貯金通帳の写し(支店名や口座番号、直近の残高と取引履歴)
- ・生命保険や学資保険の証券、解約返戻金がわかる資料
- ・不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
- ・相手方の源泉徴収票や給与明細など、収入がわかる資料
これらの資料を調停後に相手方に提示させることは比較的困難ですから、注意しましょう。
2-3. 事前に弁護士に相談する
離婚する際に適切な結果を得るためには、法的な知識と戦略が必要です。自己判断で離婚協議や離婚調停を進めるのではなく、離婚問題に詳しい弁護士に事前に相談することが重要です。弁護士に相談すれば、以下のメリットを得られるでしょう。
- ・別居の仕方や証拠の集め方など、調停で不利にならないための具体的なアドバイスを得られます。
- ・親権、養育費、財産分与、慰謝料について、法的な相場を踏まえた、ご自身にとって最大限有利な条件を設定し、交渉の戦略を立てられます。
- ・複雑な申立書類の作成・必要書類の収集や、調停期日での対応を依頼することで、精神的・実務的な負担を大幅に軽減できます。
これらのメリットを最大限生かしながら、離婚協議・離婚調停を進めましょう。
3. 別居後の離婚調停の流れ
さて、別居後に家庭裁判所で行う離婚調停の標準的な流れもご説明します。
3-1. 調停の申立て(必要書類、費用、申立先)
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることで始まります。別居後であっても、「相手方住所地」が基準となりますのでご注意ください。
離婚調停にかかる実費は、収入印紙(1,200円分)、連絡用郵便切手代(数千円程度)、戸籍謄本取得費用(450円程度)などです。調停の申立書のほかにも、夫婦の戸籍謄本、申立人の収入に関する資料などを提出する必要があります。
3-2. 通知が届く
この離婚調停申立て後、家庭裁判所は、あなた(又はあなたが依頼した弁護士)の予定を踏まえて調停の期日を決定し、その通知を相手方へ送付します。
初回調停日は相手方の予定を考えずに決定するため、初回は相手方が欠席となることも稀ではありません。
3-3. 調停を重ねる
調停期日には、申立人、相手方、そして2人の調停委員が出席します。原則として、夫婦が直接顔を合わせることなく、調停委員が交互に双方の意見を聞き取り、解決に向けた話し合いを促進します。通常、月に1回程度のペースで、複数回調停が行われます。
3-4. 離婚不成立の場合は離婚訴訟に
調停で夫婦双方が離婚の条件に合意すれば、調停は成立し、合意内容を記した調停調書が作成されます。
他方で、調停を重ねても合意に至らない場合は「調停不成立」となり、調停は終了します。この場合、離婚を求める側は、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起して、裁判官の判断を仰ぐことになります。日本の離婚制度では、原則として訴訟の前に調停を経る調停前置主義がとられていますので、いきなり訴訟を起こすことは認められていません。
なお、婚姻費用についての調停もまとまらなかった場合には、手続が審判に移り、裁判官が婚姻費用を定めることとなります。
4. まとめ
以上のとおり、別居後に離婚調停をするメリットと別居に際しての注意点について解説しました。別居後の離婚調停は、離婚成立に向けた最も現実的かつ効果的な手段の一つです。しかし、離婚調停を成功させるための鍵は、別居前の周到な準備と、法的な注意点の厳守にあります。
特に「悪意の遺棄」とみなされるリスクを回避し、財産分与の資料を確実に保全しておくためにも、別居を決意した段階で、速やかに弁護士に相談し、適切な戦略をもって調停に臨むことが、望ましい結果を得るための最善策です。弁護士に相談すれば、あなたのケースで取るべき対応を知ることが出来るでしょう。
当事務所では、多くの離婚事件を扱っております。お悩みのあなたのご相談に親身に寄り添う弁護士が多数在籍していますので、ぜひ、別居後の離婚調停については、当事務所にご相談ください。
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。