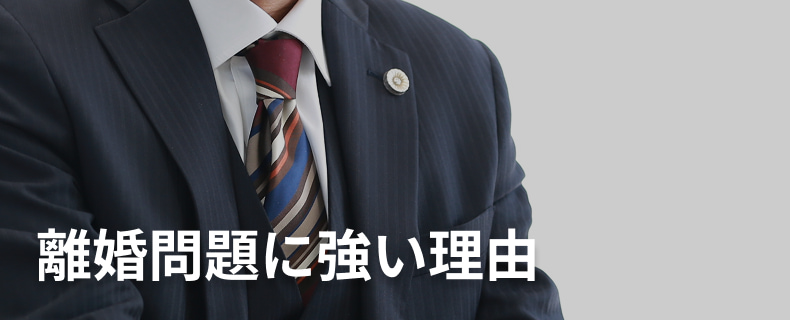夫婦という安心できるはずの家庭で、傷つき、出口を探しているのではないでしょうか。
夫婦間のハラスメントは周囲に打ち明けにくいものですが、正しい知識と手順を知れば状況は必ず変えられます。
<こんな悩みはありませんか?>
- ・毎日の人格否定のことば
- ・財布を握られ使えない生活費
- ・不機嫌で支配される家庭空気
- ・性的強要への恐怖
- ・妊娠中も続く過重な家事
この記事では、代表的な夫婦間のハラスメントの種類を整理し、離婚理由として認められるかを法律の視点で解説します。
さらに、現状を抜け出したいという方のためにハラスメントからの打開策を3ステップで解説いたします。
<この記事で分かること>
- ・夫婦間のハラスメントの6つの例
- ・離婚理由となる法的基準
- ・安全確保と証拠集めの方法
- ・別居から相談までの行動手順
目次
夫婦間のハラスメント一覧
夫婦は本来支え合う存在ですが、残念ながらパートナーからのハラスメント(嫌がらせ)に悩むケースも少なくありません。夫婦間で起こり得るハラスメントにはさまざまな種類があり、その行為によって心身に深刻な影響を及ぼすことがあります。
ここでは、代表的なハラスメントの種類とその特徴を解説します。
モラハラ(モラルハラスメント)
- ・人格を否定する暴言
- ・長期間にわたる無視
- ・交友関係や行動の過度な制限
モラルハラスメント(モラハラ)は、言葉や態度によって配偶者の心を傷つける精神的な嫌がらせです。例えば、相手を否定するような暴言を吐く、一方的に怒鳴る、無視して心理的に追い詰めるといった行為は、目に見えない暴力と言えます。
直接的な身体の暴力はなくても、これらの言動は受けた側に大きなストレスやトラウマを与え、DV(ドメスティック・バイオレンス)の一種として問題視されています。
マネハラ(マネーハラスメント/経済的DV)
- ・生活費を渡さない金銭圧迫
- ・支出を細かく管理して束縛
- ・貯金の無断引き出し・使い込み
マネーハラスメント(マネハラ)とは、お金に関する嫌がらせ全般を指します。夫婦間のお金の管理は重要な問題ですが、マネハラでは一方が生活費を極端に制限したり、お金の使い道をすべて支配したりします。
特に配偶者が専業主婦(主夫)の家庭では、収入を握る側が相手に十分なお金を渡さないと、相手は日々の生活もままならず深刻な事態になってしまいます。必要なお金を渡さず、子どもの生活まで困窮させるようなケースでは、児童虐待に繋がる可能性もあります。
フキハラ(不機嫌ハラスメント)
- ・無言や長いため息による圧力
- ・怒りを露骨に示す態度で威圧
皆さまは「フキハラ」という言葉をご存知でしょうか。フキハラとは「不機嫌ハラスメント」の略で、近年社会的に認知されるようになった造語です。造語ですので明確な定義はありませんが、特定の相手に対して明白に不機嫌な態度を取ることで、相手を心理的に委縮させたり過度に気を遣わせたりするといった嫌がらせ行為のことを指して用いられています。
具体的には、配偶者が気に入らないことがあると終始黙り込んだり、大きなため息や舌打ちで不満を示し続けるようなケースです。このように家庭内の空気を意図的に悪くされると、相手は委縮して顔色をうかがうようになり、大きなストレスとなります。
フキハラは直接的な目に見える暴力ではありませんが、相手に対して精神的な虐待を与える立派なハラスメント行為であり、モラハラの一種と言えるでしょう。
セクハラ(セクシャルハラスメント)
- ・性的行為の強要
- ・身体的特徴への執拗な侮辱
職場でよく問題になるセクシャルハラスメント(セクハラ)ですが、夫婦間でも起こり得ます。配偶者の望まない性的な言動や行為を強要するのは、たとえ夫婦であっても許されないハラスメントです。
例えば、相手が嫌がっているのに性的関係を無理やり迫ったり、相手の体型や性生活について執拗に貶すような発言はセクハラに当たります。配偶者からの性的な嫌がらせは、場合によっては性的DV(性暴力)として法的にも問題となります。
マタハラ(マタニティハラスメント)
- ・妊娠中も家事・労働負担を強制
- ・体調不良への理解不足と非難
- ・産後すぐに育児家事の過重な押し付け
マタニティハラスメント(マタハラ)は、本来は職場で妊娠・出産した女性への嫌がらせを指す言葉です。しかし家庭内でも、妊娠中や出産後の配偶者に対する思いやりのない言動はマタハラとなり得ます。
一例を挙げると、妻が妊娠中にも関わらず家事や仕事の負担を全く軽減しない、体調不良を「怠けている」と非難する、あるいは産後すぐに無理な家事育児を押し付ける、といったケースです。妊産婦にとって非常に危険であり、心身の健康を損ねる深刻なハラスメントと言えます。
アカハラ(アカデミックハラスメント)
アカデミックハラスメント(アカハラ)は、本来、大学など研究や教育の現場で立場を利用して行われる嫌がらせを指す言葉です。教授が学生に対して研究指導の名目で過剰な雑用を押し付けるような行為が典型例です。
職場や学校でのハラスメントであり、夫婦間で起こることは稀ですが、学歴を理由に見下すようなケースや、学業や資格取得の過程で配偶者が相手の勉強を妨害したりするケースも考えられるでしょう。
ハラスメントは離婚理由になる?
配偶者からのハラスメント行為は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。結論からいえば、離婚原因になり得ます。日本の法律上、モラハラやセクハラといった言葉自体が明確に離婚事由として定められているわけではありません。
しかし、配偶者からの精神的虐待やDV行為は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するとして、離婚が認められる可能性が高いです。実際、モラハラやDVが原因で離婚に至る夫婦も少なくありません。
また、裁判でそれらが事実と認められれば、こうしたハラスメントによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合もあります。
当事務所のモラハラを理由とする離婚・慰謝料請求の一例
「結婚直後より、夫より酷い言葉を言われ、精神的にも参っている。慰謝料をしっかり取って離婚をしたい。」というご相談がございました。また、夫が不貞をしていることも判明し、
交渉の結果、夫に慰謝料として130万円を支払わせた上での離婚に成功しました。(夫の不倫相手の女性からは慰謝料として150万円を回収して、合計280万円となった。)
もう限界かも…と思ったら。状況を打開する3つのステップ
もし配偶者からのハラスメントにより「もう限界でもう耐えられない」と感じたら、我慢し続ける必要はありません。以下では、状況を打開するための3つのステップを紹介します。
① 自分の状況と証拠を整理する
まず、現在の状況を冷静に見つめ、ハラスメントの証拠や出来事を整理しましょう。一方的に責められていると、当事者は客観的に状況がわかりにくくなりがちです。いつ、どんなハラスメント行為があったのか、日記やメモに書き留めて時系列で整理してください。
可能であれば、暴言を録音する、メールやメッセージを保存するなど、後から証拠として示せるものを集めます。これらの記録は、離婚の話し合いや法的手続きの際に自分の主張を裏付ける強力な材料になります。
「モラハラ離婚の証拠として有効なものと証拠がない場合の対処法」についてはこちら>>
② 別居を検討する
次に、思い切って別居することも検討してみてください。ハラスメントを受け続ける環境に身を置いていては、心身のダメージが蓄積するばかりか、冷静な判断もしにくくなります。安全を確保するためにも、一度配偶者と物理的に距離を置き、落ち着ける環境に避難することは有効です。別居することで、相手も事態の深刻さに気付いたり、自分自身も離れて客観的に関係を見直せたりするでしょう。
また、長期間の別居は「婚姻関係が破綻している」ことの一つの客観的な証拠にもなり、協議で離婚できない場合に裁判で離婚請求が認められる可能性が高くなる。別居の長さが、3~5年程度が目安と言われることもありますが、中には2年程の別居で認められた事案もあります。
③ 離婚問題に強い弁護士に相談する
DV・ハラスメント問題を数多く扱っている弁護士に相談すれば、適切なアドバイスや法的手続きをサポートしてもらえます。一人で悩み続けても解決策は見つかりにくく、精神的に追い詰められてしまいかねません。
弁護士であれば、証拠の集め方や今後取るべき行動について具体的にアドバイスしてくれます。また、配偶者との交渉は代理人として任せることができるため、直接対決するストレスを大きく減らすことができます。
さらに、深刻な暴力がある場合には、弁護士を通じてDV防止法に基づく保護命令(接近禁止命令など)を裁判所に申し立て、身の安全を確保することも可能です。
ハラスメントでお困りの方は弁護士法人グレイスへ
夫婦のハラスメントは、目に見えない心の傷を与える深刻な暴力です。モラハラをはじめとする六つの類型は、その程度によっては重大な事由となり得ます。
まずは自分の状況を整理し、録音や日記で証拠を確保してください。危険を感じたら別居を検討し、早めに弁護士へ相談することで、安全を守りながら離婚や慰謝料請求の選択肢を広げられます。
つらい状況を一人で抱え込む必要はありません。
弁護士法人グレイスは、離婚やDVなど夫婦間トラブルの案件を数多く扱ってきた実績があります。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
つらい状況から抜け出すために、私たちが全力でサポートいたします。
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。