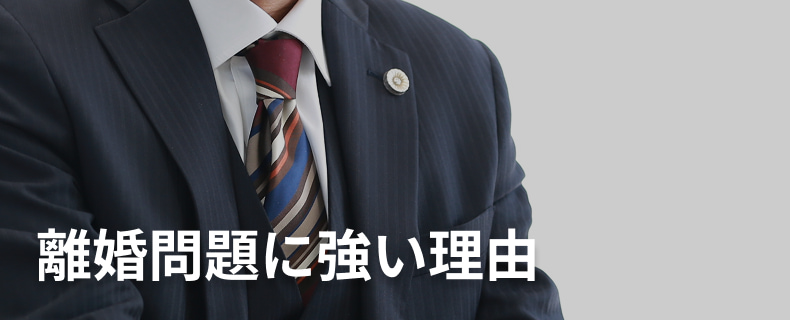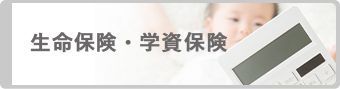預貯金、保険と並んで最も多い財産が不動産(多くの場合が自宅です。)です。
預貯金、保険が比較的様に現金化することが容易なのに対し、不動産は容易に現金化できません(たとえ都市部の人気地域でも現金化には一定の時間を要します。)。
また、現金化するにあたっては、仲介手数料はもちろん、場合によっては建物解体費用等の諸費用を要する場合もございます。
現金化できない場合、夫婦のどちらかが不動産を取得せざるを得ません(右側と左側で半分ずつとはいきませんから・・・)。
その場合、不動産の金額をどのように評価するのかという問題と、住宅ローン(特に連帯保証・連帯債務の部分)をどのよう処理するかという問題が生じます。
以下、不動産に関して協議、調停、訴訟で頻繁に問題となる点について解説いたします。
不動産の評価額
まずは、不動産の時価を算定し、評価額を算出します。不動産会社に査定してもらったり、近隣で同じような物件の取引があれば、その価格を参考にしたりします。
その他に、土地は路線価や公示価格を参考にしたり、不動産鑑定士に依頼したりする方法もあります。
不動産の分与方法
不動産を分与する場合には、
- 売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける
- どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う
- 相手方名義の家に住み、賃借権を設定して家賃を払う
- 分与の割合に応じて共有する
など、様々な方法があります。しかし、それぞれに良い点もあれば、悪い点もあります。
1.については、分け方が簡明であるというメリットがありますが、中古住宅であれば希望価格での売却が困難というデメリットがあります。
2.については、片方が従前の住まいと同じ場所に住むことができるというメリットがありますが、他方で差額の支払い能力がないと困難であるというデメリットがあります。
3・4については、支払い能力についてはあまり問題となりませんが、離婚後も相手との交渉を続けなければならないというデメリットがあります。
不動産を分与する場合には税金の問題もあるため(後述)、どういう分け方をするのかは慎重に選択すべきです。
ローン付き不動産の分与
ローンが残っている不動産の場合は、そうでないものと比べて財産分与が複雑になります。
ローンが残っている不動産の評価額
まず、不動産の評価額ですが、不動産の時価から、残っているローンの額を引いた額とするのが一般的です。例えば、時価3000万円のマンションでローンが2000万円残っている場合には、3000万円-2000万円の1000円が分与の対象となります。
また、評価時期までに返済した元金充当分を分与の対象とする考え方もあります。例えば、時価3000万円のマンションで、離婚時までに返済したローンのうち元金充当額が2000万円であれば、この2000万円が分与の対象となります。
ローンが残っている不動産の分与方法
ローン付き不動産を分与する際には、不動産の名義、ローンの名義、ローンの残高、不動産の時価によっても違ってきますが、
- 所有権を取得した側がローンの返済をし、分与の差額があれば現金で支払う
- 売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける
- 所有権を取得しなかった側がローンの返済をする
等の形があります。
1.の場合、マンションの時価が3000万円でローンが1000万円残っているとすると、2000万円が分与の対象となります。分与の割合が2分の1ずつとすると、取得する側は、相手に現金などで1000万円を支払うことになります。取得する側がローンの名義人でなければ、名義の変更をしなければなりません。変更には債権者の承諾が必要であり、支払い能力がなければ承諾はされないでしょう。
2.の場合は、不動産の時価よりもローン残高が上回っている場合、売却しても債務がのこることになります。例えば、マンションの時価が1500万円で、ローン残高が2000万円であれば、売却後も500万円の債務が残ります、この債務について、分与の対象とすることもあります。
3.の場合は、例えば妻に不動産の名義を変更し、ローンの名義人である夫が離婚後養育費の代わりとしてローンを払い続けるという形も場合によっては考えられます。ただ、離婚後夫が任意にローンを支払うとも限りません。支払われなくなった場合、ローンの支払いの取り決めを公正証書でしてあれば強制執行の手段もありますが、夫に資力がなく、差し押さえる財産がなければ意味がありません。
ローンの連帯保証人について
また、妻がマンションのローンの連帯保証人になっている場合には、夫がローンを支払わない場合、妻にローンの支払い請求が一挙にされてしまいますので、そこには十分留意する必要があります。
お金を貸した側としては、担保として、連帯保証人をつけているわけですから、簡単に連帯保証契約を解除したり、他の親族に連帯保証人を変更したりすることは、弁護士を入れたとしても難しいところです。ですから、不動産の財産分与の際は、ローンについてしっかり把握し、その支払いについてどうするか、そこでの交渉であれば弁護士に依頼するメリットは十分あります。
不動産の財産分与と税金
譲渡側
不動産を分与する場合は、実際には売買していなくても、分与する側が資産を売却して得た代金を相手に支払ったものとみなされ、支払う側に譲渡所得税が課せられる場合があります。
居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除(3000万円を限度とする・平成30年6月現在)が受けられます。さらに所有期間が10年を超える場合は軽減税率の適用が受けられます。ただし、この軽減税率は「親族以外の者への譲渡」に適用されるので、分与は離婚成立後に行うこととなります。
譲受側
不動産を受け取る側には、「不動産取得税」と、不動産の名義変更の際に「登録免許税」が課せられます。また、不動産の所有者になると、毎年「固定資産税」が課せられます。
離婚前の贈与で非課税扱いになる場合
結婚20年以上の夫婦であれば、一方が自宅用の土地や建物や、土地・建物の取得金を贈与し、贈与された側が続けて住む場合は、2110万円(特別控除2000万円+通常の贈与税の控除額110万円)までは非課税です。
もっとも、不動産取得税・登録免許税はかかります。贈与した側にも税金は課せられません。この制度を使うか、財産分与をするか、比較考量して検討する必要があります。
売却する場合
-
【不動産】売却する 【住宅ローン】残なし 【名義】購入者へ変更
-
売却益から各種経費(仲介手数料、公租公課等)を差し引いた残額を双方で分配。
メリット
簡潔明瞭
デメリット
相当な中古物件の場合、希望価格での売却が難しく、時間を要する可能性あり
-
【不動産】売却する 【住宅ローン】残あり 【名義】購入者へ変更
-
売却益(売却価格-住宅ローン)から各種経費(仲介手数料、公租公課等)を差し引いた残額を双方で分配。
メリット
簡潔明瞭
デメリット
オーバーローンになる可能性あり。手持ち資金で残金を返済できれば問題ないが、できない場合は、そもそも売却不可。
売却しない場合
-
【不動産】売却しない 【住宅ローン】残なし 【名義】取得する夫もしくは妻
-
不動産価値を査定し、取得側が相手方に査定額の半分を支払う。
メリット
取得側が従前どおり同じ場所に住むことができる
デメリット
相手方に支払うための現金が必要となる
-
【不動産】売却しない 【住宅ローン】残あり 【名義】取得する夫もしくは妻
-
不動産の査定価格が、ローン残高を上回る場合は、査定価格よりローン残高を差引いた額を分与財産とし、取得側が相手方に半額を支払う。
不動産の査定価格が、ローン残高を下回る場合、裁判所の先例は分かれているが、基本的には、ローン残高と査定額との差額をマイナスの財産として分与する。すなわち相手方が、取得側にマイナス財産の半額に当たる金銭を支払う。
メリット
取得側が従前どおり同じ場所に住むことができる
デメリット
①の場合、相手方に支払うための現金が必要となる。①・②共通して、査定価格の算出で揉める可能性がある。(取得側はなるべく安く、取得しない側はなるべく高く算出したい思惑が出てくるため)
-
【例外】不動産の名義を妻に変更した上で、住宅ローンの名義人である夫が、養育費の代わりにローンを支払い続ける
-
メリット
妻は、ローンを支払わずに従前どおり同じ場所に住むことができる
デメリット
夫が離婚後にも拘わらず、任意にローンを支払い続ける確約はない
まとめ
不動産の現金化は、預貯金や保険のようには簡単にはいかず、現金化できない場合には、夫婦どちらかが不動産を取得せざるを得ません。しかし、取得すると一言で言っても、名義やローンの支払い、連帯保証人についてなど様々な問題が降りかかります。
財産分与に不動産が含まれる際には、難しい問題が起きてからではなく、なるべく早い段階から弁護士への相談をお勧めいたします。
財産分与別INDXはこちら
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。