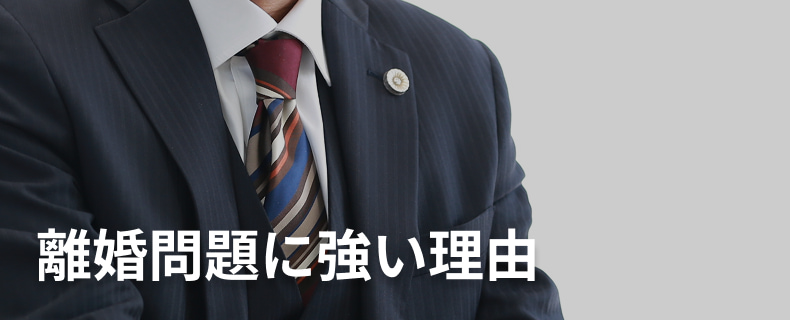お子様がおられる方が離婚される際に、まず思い浮かべるのが「養育費」のことではないでしょうか?
養育費とはどういうものなのか、養育費の相場はいくらなのか等、どうすれば相手から養育費を払ってもらえるのか等、多くの専門的な知識が必要となります。
そこで、養育費についてお悩みの方は、是非、弁護士にご相談下さい。
「養育費」とは何でしょうか?
まず、最初に皆さんが最も気にされている養育費の相場についてご説明します。
民法上、養育費算定の具体的な方法、基準についても何ら規定はされていません。
しかし、家庭裁判所においては、義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)双方の総収入に「養育費算定表」を目安に養育費の大まかな金額が定まります。
ただし、「養育費算定表」はあくまでも目安に過ぎず、当事者及びその子らにとって最も適切な金額がいくらであるかは、個々のケースに基づいて個別に判断されることとなります。
民法上、「養育費」といった文言は規定されていませんが、両親が離婚する時に「養育していない方に請求する子どもの生活費」という概念として使用されることが一般的です。
養育費の相場について詳しく知りたい方はこちら>>養育費支払いはいつまで?成人年齢引き下げで変わる?
質問:養育費をいつまで支払うかで争っています。
妻は大学を卒業するまで支払ってもらいたいそうですが、夫である私は高校を卒業して成人する18歳まででいいと思っています。妻と私の言い分どちらが正しいですか?
回答:原則的に養育費の支払い時期の終期は20歳までとされることが多いですが、お子様の通学状況等の事情により変わることもありえます
2022年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳となりましたが、養育費もただちに18歳までとなるわけではありません。特に18歳以上の進学率(大学進学の他、短大や専門学校進学も含みます)は80%を超えています(文部科学省「令和3年度学校基本調査(確定値)の公表について」)。
養育費がお子様の健全な成長に不可欠なものであるという観点からも、当然に養育費の終期を引き下げるというということにはなりません。
もっとも、養育費の根拠はご両親のお子様への扶養義務に基づくものです。そのため、お子様が両親の扶養を必要とする未成熟子(独立して生活する能力のない子)の段階にあるかどうかで定まります。
お子様が中学校や高校を卒業した後すぐに就職されたなど、18歳以下で就職したような場合は養育費の支払い義務が18歳でなくなる場合もございます。
他方で、ご両親の学歴が双方とも大学卒業であることや、幼いころから大学を卒業させることを目的に進学先を選び大学進学がほぼ確定的な場合など、お子様が大学に進学する可能性が高い場合等は、例外的に22歳までとするなど、大学を卒業する年を前提として終期を定める場合もございます。
特に、すでにお子さんが大学に進学されている場合などは、大学を卒業する22歳までと認定されやすくなります。
お子様の状況、ご両親の事情、これまでの子育て事情など様々な事情に影響されますので、お悩みの際はぜひ相談にいらっしゃってください。
養育費を請求する流れ
養育費の請求といって決まった方法があるわけではありませんが,一般に以下の2つの方法に大別されます。
- 交渉による裁判所を使わない方法
- 裁判所を利用する方法
多くの場合、②裁判手続は、時間的コストがかかることが多いため、まず交渉による方法から進めて行くことをお勧めします。相手方への連絡手段があるのであれば、その方法を用いて行うことになりますが、事後的に請求の存否自体が争われないように、可能であれば書面による送付もしくはメール等の方法など、客観的に形に残る方法でされることをお勧めします。
それでも相手方からの対応がない場合は、養育費請求調停もしくは審判を管轄(本件を取り扱うことになる裁判所)の家庭裁判所に申し立てることになります。
必要書類を収集した上で、管轄の裁判所に本請求に必要な書類を提出することで、養育費請求手続の日程が決定することになります。このようにして、養育費請求手続きの日程が決まりましたら、同手続で具体的な金額等の決定がされます。
養育費の増額が認められるケース
養育費の増額が認められる正当な理由としては、以下のようなものがあります。
- 子どもの進学や授業料の値上げによって養育費が増加した
- 子どもの病気や怪我で多額の医療費がかかった
- 監護者の病気やけが、リストラや会社の倒産で収入が低下した
養育費は、子どもにとって両親である双方の収入から相関的に決まるものですので、義務者(子どもを実際に監護していない親)の収入が上がった場合、権利者(子供を実際に監護している親)の収入が下がった場合が代表的なケースです。
他にも子どもの教育費が増大し、それについての分担が必要になった場合、医療費が増大し分担が必要になった場合などに増額が認められます。
養育費の減額が認められるケース
養育費の減額が認められる正当な理由としては、以下のようなものがあります。
- リストラや会社の倒産、事業の失敗、病気、怪我などで、支払う側の収入が低下した
- 監護者が就職等で経済的に安定した
養育費が減額するのは、上記増額事由と反対の場合ということになります。義務者の収入が下がる、権利者の収入が上がる場合がこれに当てはまります。
また、想定されていた教育費の変更、医療費の変更、義務者に扶養義務者の出現といった事情が想定されます。
また、増額・減額を基礎づける正当理由があることに加え、その理由が「元々の養育費額設定時に予想できた事情かどうか」が重視されます。上記の例でいうと、病気が当初から分かっていた場合や、会社の倒産が当初から予想されておりそれが双方の共通認識だった場合には、審判で養育費額の変更は認められづらい方向に働くと思われます。
上記のとおり、養育費額の変更には「正当理由」が必要となるので、「当初合意で取り決めた養育費が算定表より高いまたは低い場合」には、その理由だけで、算定表に基づいた養育費に取り決めなおしたいとの主張は、通りにくいです。
ただし、過去の養育費が最初から虚偽や事実の隠蔽により不当に決まり、その養育費を維持することが著しく当事者の公平に反するような場合や、当初の養育費の合意が時期を限定した合意である(と諸々の事情から解釈できる)場合は、算定表による養育費への見直しが認められることもあります。
また若干特殊なケースとしては(「特殊」と言っても実際にはそれなりの頻度で生じます)、監護親が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をするケースがあります。
この場合は、再婚相手(養父)が第一次的な扶養義務者になり、実父の扶養義務が後退する結果、養父に子どもの扶養能力がないなどの事情(心情的にはそのような経済状況で子を養子にするなと言いたくなってしまうかもしれませんが)がない限りは、子の養育費は免除されることになります。
ただ、この場合でも養父と子の養子縁組により自動的に養育費支払義務が消滅するわけではなく、監護親の方と合意をするか、養育費減額(免除)調停を起こす必要があります。
養育費が支払われない場合
離婚時に子が幼少の場合には養育費の支払は長期間に及ぶので、不払いトラブルも少なくありません。養育費について話合いをしたら、必ず、その内容を文書で残すべきです。そして、文書には、支払期間(終期)、金額、支払方法を明記すべきです。
また、文書化する際は、可能な限り公正証書にすることが望ましいです。公正証書にしておけば、あとあと支払いが滞った場合に裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえること(強制執行)ができます。
また、家庭裁判所の手続きを経て離婚する調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合には、公正証書による取決めがなくとも、強制執行により非監護親の預貯金や給料を差し押さえることができます(養育費については、将来分も予め強制執行することができるなど、民事執行法上の特則により制度が手厚くなっています。相手方が勤務先を退職して逃げた場合でも、次の転職先をある程度は追うこともできます。)。
養育費を弁護士に相談するメリット
協議を行う場合、調停や審判を行う場合も、整理した主張を行わない限りいたずらに時間ばかり経過することになりかねません。弁護士に頼むことで、より有利な主張をより有用なタイミングで行うことことができ、早期に養育費の請求、獲得を実現しやすくなることがメリットとして考えられます。
よくある弁護士に依頼するメリットが大きいケース例
⑴ 自営業者の場合
自営業者の場合も原則として確定申告書記載の「課税される所得金額」を前提に、標準算定方式に基づいて養育費が算定されます。実際、算定表の収入欄には給与所得者の収入と併記される形で自営所得者の収入が記載されています。
もっとも、給与所得者の収入は源泉徴収票等に記載の総収入を単純に参照すれば良いのに対し、自営所得者の場合は必ずしもそうではありません。
「雑損控除」、「寡婦、寡夫控除」、「勤労学生、障碍者控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「青色申告特別控除」といった現実に支給されていないものについては「課税される所得金額」に加算されるべきものです。
また、小規模企業共済当化基金控除や寄付金控除も、性質上、養育費の支出に優先すべきものではない為、加算されます。
その他、自営業者の場合、節税等の観点から必要経費が必要以上に計上されている場合が事実上多々あります。そのような経費が本当にその事業を維持する為に必要な経費なのか、単に生活費として支出したものまで経費として計上していないかについて精査すべき場合もございます。
以上のとおり、自営業者の場合、養育費を算定するにあたって前提となる収入の考え方に大きな幅が生じかねない為、事実関係をきちんと精査し、法律上の主張立証をきちんとしているかによって大きく差が出る場合があります。
したがって、当事者が自営業者の場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
⑵ お子様の教育費が問題となる場合
標準算定方式によって定める養育費は、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費のみが考慮されています。その為、お子様が私立中学校・私立高等学校に進学した場合、塾や習い事を利用している場合、大学等の教育期間に進学した場合の養育費や進学費用については別途検討される必要があります。
もっとも、当然に義務者が全ての教育費について支払い義務を負うわけではあるなせん。従前より義務者が承諾していたかどうかという事情の有無や、義務者の収入・学歴・地位等の一切の事情が考慮されることになります。また、具体的にどの部分の費用が対象となり、どのような方法で加算されるかについては細かい計算を要する場合もあります。
このように、お子様の教育費が問題となる場合、これまでの教育に関する夫婦のやり取りや行動をあらためて整理し、法律上の主張立証をきちんとしているかによって大きく差がでる場合があります。
したがって、お子様の教育費が問題となる場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
⑶ 夫婦間の子以外の被扶養者がいる場合
認知した子がいる場合や、前妻との子を監護養育している場合等、夫婦間の子以外に被扶養者がいる場合も標準算定方式による計算が複雑化しやすい傾向にあります。
このような場合、義務者が当該被扶養者と実際に監護養育しているのか、単に養育費を支払っているだけなのかによっても検討方法が変わる可能性があります。
したがって、夫婦間の子以外の被扶養者がいる場合、適切な金額を算出するにあたっては弁護士に依頼することで金額が大きく変わることもありますので、一度ご相談ください。
一度決まった養育費の金額が変更されることは無いのでしょうか?
「子どもが大きくなり、進学等によって必要なお金が増えたから養育費を増額して欲しい。」、「養育費を決めた後に、不景気で給料が大幅に下がってしまったので養育費を減額して欲しい。」、そんなご相談を受けることが度々あります。
養育費は、長い場合は約20年近くにわたって支払われるものであり、その間、色々な事情の変更が起こりえます。そんな場合に備えて、民法880条には以下のとおり定められています。
【民法880条】
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
このように、事情変更により、養育費の増額又は減額請求をする権利は、法律上認められています。
養育費って相場で決められている額しかもらえないの?
質問:養育費って相場で決められている額しかもらえないの?
夫から性格の不一致を理由に離婚を求められていますが、今後の生活に不安があります。離婚する場合はせめてもう少し養育費を増額して欲しいのですが・・・
回答:相場である程度決められていますが、弁護士の交渉等により相場より高い額を勝ち取ることができる場合もあります。
養育費は、離婚する夫婦の間で争われやすい項目であり、以前は調停・審判の長期化の原因となっていました。
そのため、平成15年4月に東京・大阪の裁判官を中心に養育費算定表が考案され、現在は広く活用されています。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
(現在の改定標準算定表)
この算定表は、離婚する夫婦それぞれの収入額とお子様の数・年齢から養育費の額を決定しています。
算定される養育費額が低すぎるという意見もありますが、多くの場合においてこの算定表で計算される養育費額を前提に交渉されるのが現実です。
しかし、相場よりも高い養育費が全く認められないわけではありません。
算定表は公立学校の学費を前提としているため、お子様が私立の学校や塾に通っている場合には相場より高い養育費が認められる場合もあります。養育費を払う側が私立への進学や塾通いを了承していると相場より高い養育費が認められやすい傾向にあります。
また、相手が離婚したがっている場合には交渉により相場以上の養育費が認められやすいです。
当事務所では、性格の不一致を理由に離婚が求められている事例で、別居期間が短いことや他に明確な離婚理由がないことを交渉材料に、相場より1万円高い養育費を勝ち取ることができた事例があります。
例えばお子様が10歳であれば、月の養育費が1万円高ければ20歳まで10年間合計で120万円の増額となり、お子様の養育への大きな助けになります。
このように、養育費は算定表である程度決められていますが、弁護士が入ることにより相場より高い養育費をもらえる場合もあります。
ご自身の事情の場合どうなるか、お悩みの際は是非お気軽にご相談下さい。
「養育費」の問題は当事務所にお任せください
以上のとおり、「養育費」は、支払額や支払期間について個々のケースに応じて千差万別の判断が為されるものであり、弁護士の助言と高度な交渉力が不可欠です。
当事務所は、養育費についても、相手と積極的な交渉を行い、大切なお子様の将来の為に養育費の増額と支払い期間の延長を目指します(以下の具体例は、いずれも当事務所で実際にあった例です)。
具体例① 養育費の支払いを拒否されていたケース
「養育費算定表」を提示することで、同算定表に基づく養育費の支払いを認めて頂くことに成功しました。
養育費を払わない夫への対処法はこちら>>具体例② 「養育費算定表」に基づく金額の提示はあったが、20歳までの支払いまでしか提示されていなかったケース
相手との交渉を通じ、お子様が22歳となる年の3月まで、養育費の支払いを認めて頂くことに成功しました。
具体例③ その他
「養育費算定表」に基づく金額以上の金額の提示を認めて頂いたケース、ボーナス月の養育費の増額を認めて頂いたケース等、当事務所が交渉を行った結果、裁判では決して得ることの出来ない好条件を相手に認めて頂いたケースが多数ございます。
このように、当事務所は、離婚案件を多数扱っており、豊富な経験に基づく適切な助言が可能です。お子様の無限大の可能性をつぶさない為にも、まずは当事務所のドアを開かれてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら
お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。